

利用者に寄り添える存在に
国内事業部
グッドごはん東京課職員
亀田雅人インタビュー

グッドネーバーズ・ジャパンが2017年から始めた、子どもの貧困対策プロジェクト「グッドごはん」。この事業を担う国内事業部のスタッフとして日々活動している、亀田雅人さん(2022年入職)にお話を聞きました。
※本記事は2025年3月時点の情報に基づいています。
金融業界から「支援」の世界へ
―グッドネーバーズ・ジャパンに入職するまでのことを教えてください
4年制の大学の経済学部を卒業した後、地元の信用金庫に6年間勤務しました。窓口業務、営業外回り、融資の相談業務などの信用金庫業務全般を経験しました。
信用金庫を就職先に選んだのは自分がひとり親で育ったことに理由があります。私が中学生の時に父がうつ病で仕事に行けなくなり、高校生の時から母親と兄との3人での生活が始まりました。実際に父と母が離婚したのは私が成人した後なので、ひとり親に対する支援制度が何も受けられない状態がずっと続いていました。中学生の時から家のガスや電気が止められることもよくありました。母親は生活費をパートで稼ぎ、父親からの収入はほぼない状況でした。今思えば、安定した職と言われる金融業界を目指して信用金庫を選んだのだと思います。
―金融業界からNPOであるグッドネーバーズ・ジャパンに転職したきっかけは何ですか?
前職に在籍していた時に地域のフードバンク活動にボランティア参加しました。余剰食品を必要とする人に届ける無駄のない関係性に感動し、これが自分の仕事になるのであれば理想的だと思いました。仕事として探すことは難しいのではないかと思ったのですが、グッドネーバーズ・ジャパンの国内事業部応募の求人を運よく見つける事ができました。
仕事への想い
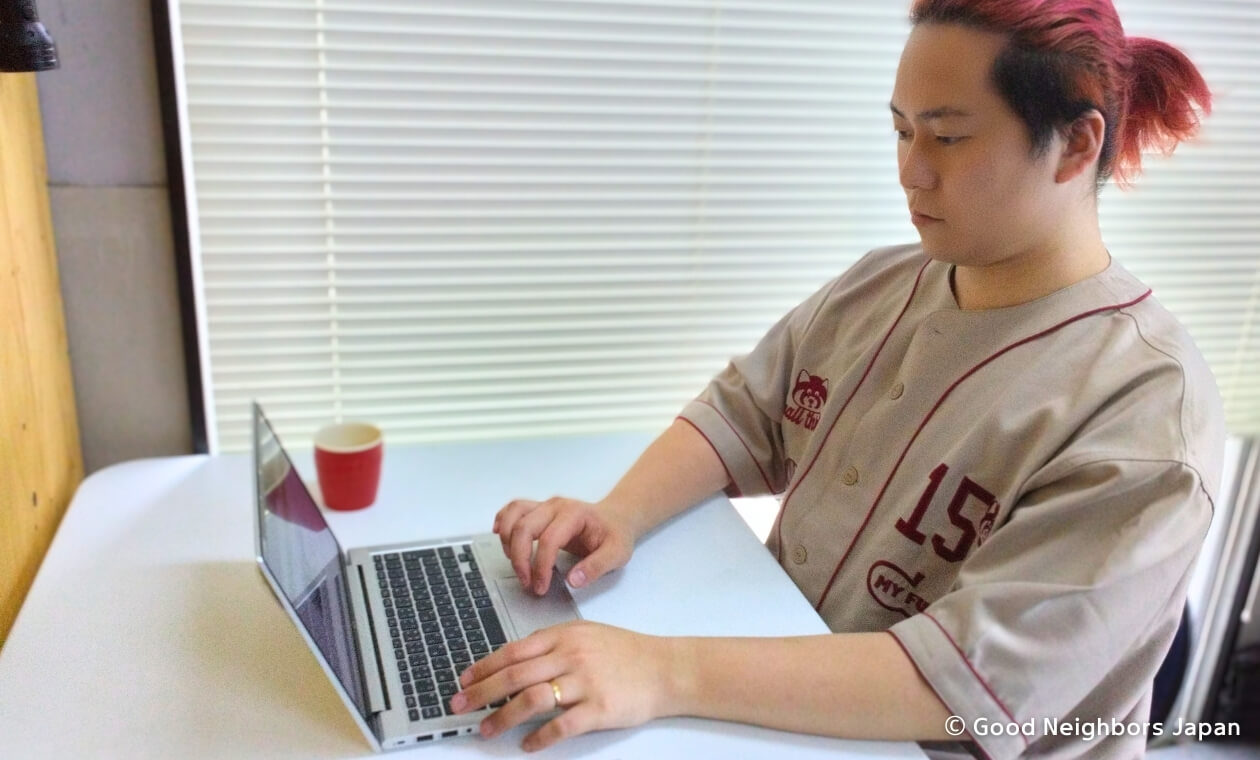
―グッドごはんの業務で一番大変なことと、一番楽しいことを教えてください
大変なことは、フードバンク業務は肉体労働が多いので、体力をかなり使う点です。また、配付先も都内各所に広がっているので移動も大変です。あと、大変なこととは少しずれるかもしれませんが、やれることとやれないことの線引きが難しいと日々感じます。グッドごはん利用者のお子さんの年齢や人数に合わせて食品配付量を個別に設計するのが理想的ですが、現状の規模と運営体制では難しいのが現実です。
また、利用者の方から食品受け取り時間に遅刻連絡があった場合、待ってあげたい気持ちはあるのですが、会場はご厚意で借りており、次の利用予定がある場合や超過料金が発生する場合もあります。さらに、食品回収のチャーター車両の待機にも費用がかかるため、どうしても待機できないことがあり遅刻をされた方には食品を渡せない事があります。限られた事業費の中で、どう有効に資金を使うかを常に考えて活動をすることをいつも心がけています。
楽しいことは「ありがとう」と言ってもらえること、そして利用者の方たちの子どもの成長が追えることが一番ですね。あとは、年齢層の幅広いボランティアさんと出会えてこちらもたくさん刺激をもらえます。
食品を扱っていると見慣れない食品に出会えることも一つの楽しみです。
―グッドごはんを利用するお子さんたちに対して、どのような想いがありますか
私は幼いころから色んな事を諦めてきました。高校進学も第一志望ではなく公立で交通費のかからない近場の高校への入学を決め、自分のバイト代で道具を揃えられる部活を選びました。大学は特待生になってアルバイトの時間を減らす事ができましたが、予備校も大学も全部自分でお金をやりくりしました。
当時の自分を振り返ると今グッドごはんを利用している子どもたちの気持ちを少しでも理解できると思いますし、自身の母親を見ているのでひとり親である親御さんの気持ちや苦労も分かると思います。特に子どもたちへの想いは強いです。子どもたちには様々な悩みや苦労があるとは思いますが、私の様に悲観的になり色んな事を諦めてしまって欲しくないという気持ちが大きいです。
チームワークと社会課題解決に
取り組み続ける姿勢

―国内事業部の職員はどのようなスキルが必要で、どのような人が向いていると思いますか
国内事業部のスタッフは他のスタッフやボランティアさんと連携して仕事をする場面が多いため、「チームで仕事をする力」が最も重要だと思います。また、倉庫作業には肉体労働が日々発生するため、体力とともに気合も必要です。
支援を受ける人(グッドごはんの利用者)の置かれた状況を想像し理解しようとする姿勢や、国内の子どもの貧困問題に関心を持ち続けることも大切です。食品支援は子どもの貧困対策の一つの手段に過ぎません。特にひとり親家庭の貧困状態において、子どもたちの心身の健康のために組織として何ができるかを日々考えています。
支援を拡大する力や、問題を訴求する力を持ち続けることができる人が国内事業部の職員には向いていると思います。
「あのお兄さんに会いに行こう」
と思ってもらえる存在に
―亀田さんは入職後に、社会福祉士の資格を取得したそうですね
はい、そうです。初めはマル親医療証*が何か、その医療証がどのような基準でひとり親の方に付与されるのか、類似した支援制度はどれだけ整備されているのかなど何も知りませんでした。
グッドごはんの活動にも慣れてくると、食品支援はいわば応急処置であり、これはこれで必要だけれども、ひとり親が抱える貧困問題を根本的に解決するにはどうしたらいいのだろう…と考えるようになりました。
もっと、団体としても何ができるのか考えたいと思い社会福祉の分野で人々の生活を支援する専門職である社会福祉士取得を目指しました。
この2年間仕事をしながら通信制の専門学校で勉強しました。資格の試験を受けるために相談援助業務の現場経験を積むため、母子生活支援施設と障がい者支援の複合施設へ実習にも行きました。仕事をしながらの勉強は非常に大変でしたが、無事に国家資格を取得することができました。
今はひとり親家庭が抱える複雑な問題にどのようなものがあるかをより理解し、複雑な国の支援制度を知識として身に着けたので、今後は問題を抱える人に適切な支援をどう受けてもらえるかを社会福祉士としても提案ができたらと思います。そして今よりもさらに利用者の方々に寄り添える存在になっていきたいと思っています。
―今後国内事業部で、もしくは団体内でどんな存在になっていきたいですか?
グッドごはんの「看板スタッフ」になりたいです。
前職の信用金庫にいたときは、自分自身の生活の安定のために毎日の仕事を無難にこなし、その会社で安定の地位を築くことを考えていました。
でも、グッドネーバーズ・ジャパンへ転職し国内の子どもの貧困対策に関わるようになってからは、自分がやりたいことを仕事にしているという実感が湧き、必要とされていると感じるようになりました。自分の経験を振り返ると、「子どものころにこんな活動をしてくれる人がいたらよかったな」と思うことがあります。
私はひとり親で育って苦労もしましたが、周りの人たちには恵まれていたと思います。近隣に住んでいた祖母、住む場所が無くなった時に居候させてくれた叔父、大学の学友、学生時代に出会った今のパートナー。信用金庫に勤めていた時も人間関係に色々悩んでいましたが、周りの人がいつも助けてくれました。
そういう家族以外の方に助けてもらったという経験があるので、グッドごはんの利用者の方にもお子さんにも「あの人が関わってくれてよかったな」と思われたいなと常に思っています。食品を届けるだけではなく「あのお兄さんからちょっと勇気もらったな」という存在になりたいです。
グッドごはんの支援を受ける親御さんたちの中には、食品を受け取る事を後ろめたく思っている人たちも少なからずいます。でも、子どもが「お兄さんに会いに行こう」と言ってくれてそれで親御さんが来やすくなるのであればそれはとても嬉しいです。利用者の方でも「あなたに会いに来たよ」と言ってくれる人もいます。グッドごはんの配布場所に来ることをもっともっと前向きに感じてもらえるように、グッドごはんを利用する方たちの心理的ハードルを下げられないかなと思っています。
*マル親医療証(ひとり親家庭等医療費助成制度医療証)
低所得の家庭に対して、医療費の負担を軽減するために自治体が発行する証明書。グッドごはんでは同医療を保持していることが配付対象の条件の一つになっています。

編集後記(経営企画室)
自身のひとり親家庭での経験をきっかけに、子どもの貧困と向き合う道を選んだ亀田さんは、安定を求めて選んだ仕事から一転、「本当にやりたいこと」を見つけてNPOの世界へ飛び込みました。
「ただ食品を配る人」ではなく、「あのお兄さんに会いに行こう」と思ってもらえる存在でありたいという亀田さんの姿勢は、支援をもっと身近で温かいものに変えてくれていると感じました。これからも、子どもたちや親御さん達にとって頼れる存在であってほしいと思います。
国内事業部職員は現在採用募集中です